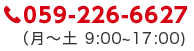『留魂録』 吉田松陰
身はたとひ
武蔵の野辺に朽ちぬとも
留め置かまし大和魂
今日、私が死を目前にして平穏な心境でいるのは、春夏秋冬の四季の循環を考えたからです。
農事にたとえれば、春に種をまき、夏に苗を植え、秋に刈り取り、冬にそれを貯蔵する。
秋、冬になると農民たちはその年の労働による収穫を喜び、酒をつくり、甘酒をつくり、村々には歓声が満ちあふれます。
そんな収穫期を迎え、その年の労働が終わったのを悲しむ者など、私は聞いたことがありません。
私はいま、30歳で生涯を終えようとしています。
いまだひとつも事を成し遂げることなく、このままで死ぬというのは、これまでの働きによって育てた穀物が花を咲かせず、実をつけなかったことに似ていて、惜しむべきことなのかもしれません。
しかし私自身について考えると、やはり花が咲き、稔りを迎えた、そんなときなのだろうとしか思えません。
なぜかというと、人の寿命には定まりがないからです。
農事が四季をめぐって、くりかえし営まれるようなものです。
人間にも春夏秋冬があります。
十歳で死ぬものには、その十歳の人生のなかに、おのずから四季があります。
二十歳には、おのずから二十歳の四季が、三十歳にはおのずから三十歳の四季が、五十、百歳にもおのずから四季があります。
十歳をもって短いというのは、夏蝉を長生の霊木にしようと願うことにしかなりません。
百歳をもって長いというのは、霊椿を蝉にしようとするような事で、いずれも天寿に達することにはなりません。
私は三十歳ですが、四季はすでに備わっています。
花を咲かせ、実をつけています。
それが単なる籾殻なのか、成熟した栗の実なのかは私にはわかりません。
しかしもし、みなさんの中に私のささやかな真心を憐れみ、それを受け継いでやろうという人がいるなら、それはまかれた種子が絶えずに、穀物が年々実っていくのと同じで、収穫のあった年に恥じないことになるでしょう。
みなさんも、どうかこのことをよく考えてみてください。